お問い合わせ


お問い合わせ

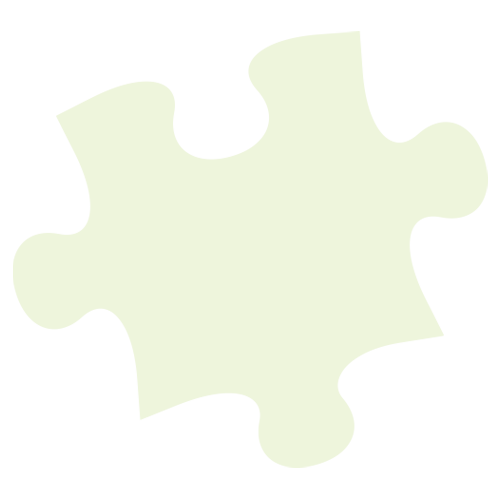
研究活動 Academic research
主な研究プロジェクト
2013年に長寿医療研究センターの荒井秀典理事長(当時京都大学医学研究科人間健康科学専攻教授)のもと、兵庫県香美町の自治体と共同し、高齢者コホート調査(Kami-study)を立ち上げました。2013年に地域で自立して生活をされていた約5500人の高齢者の方々がその後どのような経過を辿るのか追跡しており、要介護状態や死亡に至る要因を抽出し、高齢者の方々が心と体の自立を維持して長生きするための方略を探究しています。10年目の節目となった2023年には追跡調査を実施することができました。今後は高齢者がどういったプロセスでフレイル状態や要介護状態に移行していくのかを解明していきます。
認知症専門クリニックをフィールドに、認知機能低下及び認知症を有する方々の認知症の進行速度に関する要因や認知症の行動心理症状を誘発する要因の検討を行っています。フレイル状態になりやすい認知症患者さんの機能低下予防や住み慣れた自宅で穏やかに生活するための方略を考えています。
ALSは、全身の骨格筋が徐々に萎縮していく進行性の神経疾患で、治療が難しい病気のひとつです。とくに呼吸筋の麻痺が進行すると、呼吸機能が低下し、日常生活や療養のあり方に大きな影響を及ぼします。こうした呼吸機能の障害に対しては、呼吸の苦しさをやわらげ、生活の質を高めたり、生存期間を延ばしたりすることを目的に、非侵襲的人工換気(non-invasive ventilation: NIV)や、気管切開下人工換気(tracheotomy and invasive ventilation: TIV)といった方法が用いられています。私たちは、こうした症状や障害をもつ方々が、できる限り自分らしく、安心して日々を過ごしていけるように、呼吸ケアのあり方や支援体制について研究に取り組んでいます。なかでも、NIVを適切なタイミングで導入できるよう支援すること、そして医療者と患者・ご家族がともに納得しながら意思決定できるプロセスに注目し、よりよいケアのかたちを探究していきます。
糖尿病はフレイル(加齢に伴って予備能が低下し、要介護や死亡に陥りやすい状態)をきたしやすい疾患です。身体活動量低下、低栄養、高血糖、低血糖、合併症などが糖尿病でフレイルをきたしやすくする要因と言われています。そのため、糖尿病の合併症予防のための疾病管理だけでなく、早期からのフレイル対策が求められています。糖尿病患者さんを対象にフレイルの実態やフレイルや要介護状態に陥りやすい要因の解明に取り組んでいます。